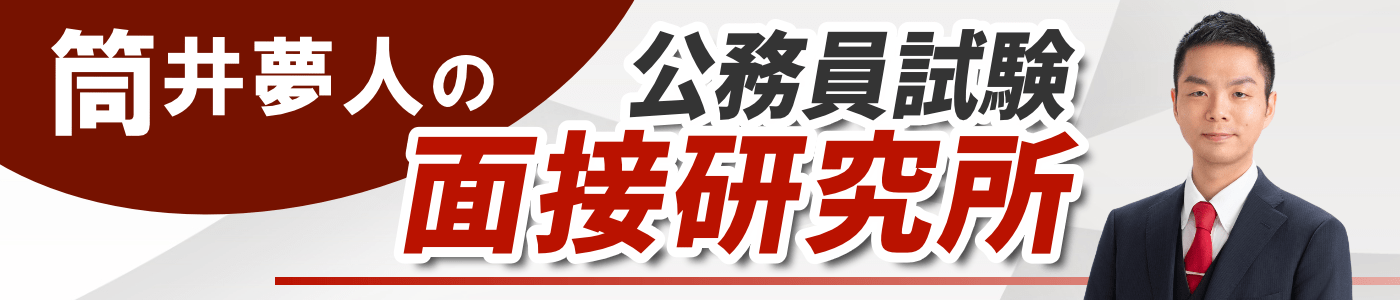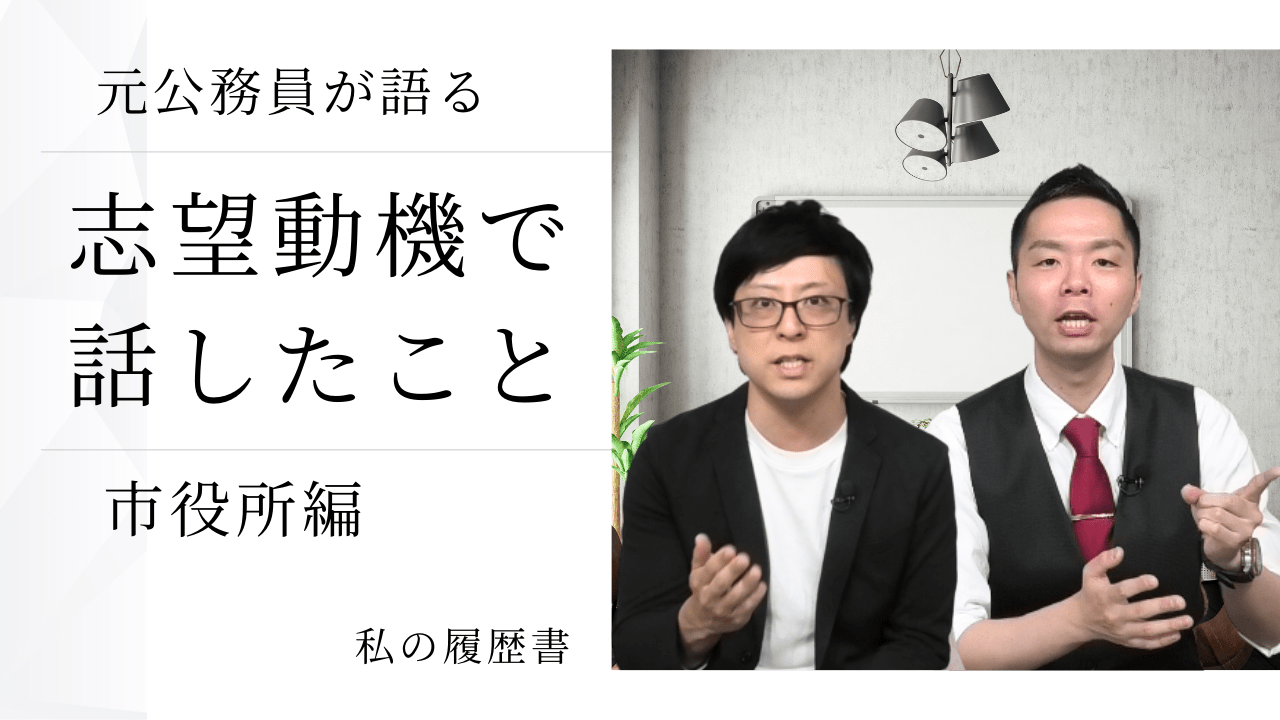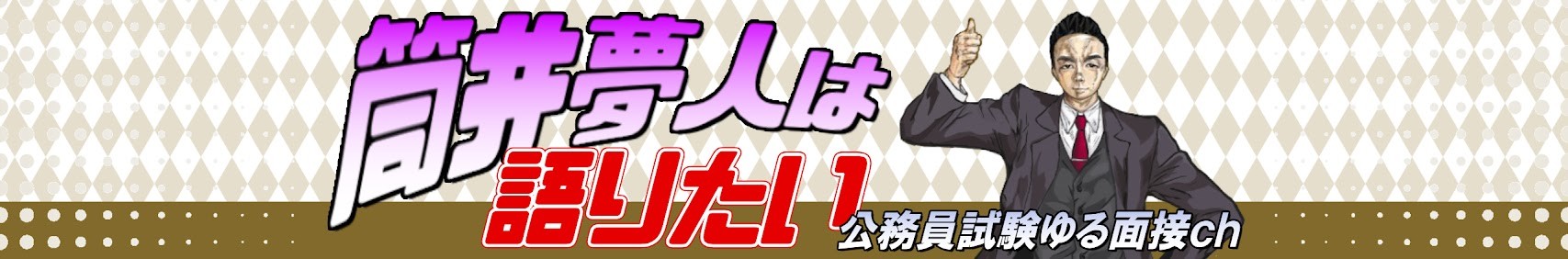本日は合格者である私と筒井先生が「志望動機で話したこと」市役所編というテーマで話していきたいと思います。
志望動機は面接試験で必ず聞かれ、合否を左右する重要な要素となっております。すべての受験生にとって志望動機が重要であることを踏まえ、今日は参考として、私たちが実際に受験生だったときに面接本番でどのように志望動機を話していたのかをご紹介します。
なお、下記のYouTube動画でも解説を行っているので、併せてご視聴ください。

では早速筒井先生、先生が市役所を受けた時はどのように志望動機を伝えましたか?

市役所は色々受けたんですけれども、一番縁や馴染みがなかった仙台市を受けた時の話をしてみたいと思います。
私自身、仙台市には本当に縁も馴染みもありませんでした。仙台にある大学に通っていたわけでもなく、仙台に住んだことがあるわけでも、家族がいるわけでもないという状況でした。
「さぞやすごいことを話したのでしょう?」と思われるかもしれませんが、実際に伝えたのは二点だけです。

一つ目は、公教育に携わりたいという思いです。
私は大学で教育経済学という分野を研究し、教育に強い興味がありました。そのため、教育をパブリックセクターで実践したいと考え、公務員を志望したと説明しました。
しかし、これだけだと「それなら他の県庁や国家公務員でもいいのでは」と言われる可能性があります。

そこで二つ目として、仙台市の教育政策に強い魅力を感じていると述べました。
これは当時、仙台市が全国でいち早く教育にEBPM(エビデンス・ベースド・ポリシー・メイキング)を導入しようと宣言していたことに基づいています。EBPMとは、データやエビデンスに基づいて教育政策を行う手法です。それまでは経験則で「こうすればよいのでは」と進められていた教育政策に対し、「データに基づかなければならない」という流れが生まれたタイミングでした。
当時、これを掲げていたのは仙台市と横浜市くらいだったのです。私は大学院でデータを扱っていたこともあり、「仙台市で教育のEBPMを推進したい」と伝えました。
まとめると、一つ目が公教育に従事したい、二つ目が仙台市が推進するEBPMに関与したいという理由で仙台市を選んだ、という話をしていました。

この辺り、奥田先生は市役所を受けた時にどのように志望動機を伝えましたか?

私は国家公務員を続けながら市役所試験を受け、武蔵村山市という、縁もゆかりもなく、一次試験で訪れるまで一度も行ったことがないまちを志望しました。
面接では当然、「なぜ武蔵村山市を選んだのですか」「地元でもないのに、なぜこの市で働きたいのですか」と質問されました。

私は協働のまちづくりに携わりたいという角度から説明しました。
具体的に注目した取組が二つあります。
一つ目は、当時武蔵村山市が実施していた介護ボランティアです。介護業界の人手不足を背景に、住民ボランティアが介護をサポートする仕組みを作っていました。
二つ目は、市が設置していた民間交番です。警察が交番を増設できないなか、市が民間の交番を設け、住民と一緒にパトロールを行って治安維持と防犯力向上を図っていました。

この二つに共通するのは、住民の力で地域課題を解決するという点です。
自治体の財政が厳しくなる将来に向け、税金だけに頼らず地域問題を解決していく武蔵村山市の取組は、全国に先駆けたモデルケースだと考えました。国家公務員として働く中でこの取組に注目し、「その一員として協働のまちづくりを推進したい」と面接で伝えたところ、面接官(市長・副市長・総務部長)から「よく調べていますね!」と評価していただきました。
志望動機においては、他のまちにはない違いを見つけ、自分の経験や興味と結びつけて語ることが重要です。志望自治体を深くリサーチし、特徴的な取組を根拠に志望動機を組み立てることで、面接官を納得させる説得力が生まれます。
ぜひ今日の内容を参考に、説得力ある志望動機を作り上げてみてください!
✅面接対策専門チャンネルの紹介
公務員試験ゆる面接chでは、元公務員&元TAC講師&全国弁論大会最優秀賞の経験を活かし、公務員試験の面接対策について専門的に情報発信を行っております。
継続的に視聴するだけで、面接で重要となるマインドセットを手に入れることができるでしょう。
詳細は下記のリンクをクリック!